|
 |
 |
|||
| 横浜文化教室 | |||||
| 拠点6箇所:
事務所:石川町 カルチャーor支部or弟子社中 戸塚 / 上大岡 / 海老名 / 沼津 / |
|||||
横浜中央茶道会 表千家茶道教室
教室(五種:表千家茶道本科、茶事教室、茶道教室男性専科、カルチャーセンター、立礼で学ぶ茶の湯)学校茶道部、企業茶道部
・講座(三種:4回、12回、25回)・体験(三種:入会検討、点茶、客作法)
| [教室案内] | [講師・教室] | [教室内容] | [費用] | [海老名支部] [沼津] | [短期講座] | [点茶体験] | [客作法体験] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [稽古内容] | [表千家] [茶会] | [茶事教室] | [場所] | [稽古用品] | [大寄茶会] | [戸塚] | [上大岡] | [港南中央] | ||||||
| [体験・見学] [お問合せ・お申込み] | [稽古内容・年間スケジュール] | [茶会 点茶席 イベント 設営・運営] | ||||||||||||
| 茶道教室は、五区分の科に分かれています。本ページは、主に本科(及び男性選科)について記載しています。 茶室:本科、男性専科 座敷:支部、上大岡カルチャー 立礼:戸塚カルチャー 茶事教室:港南中央(茶室) |
||||||||||||||
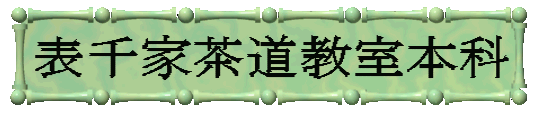 |
表千家茶道教室
本科: 初めての方から資格者迄、経験に応じた稽古を行います。 基礎から許状・資格・教授者習得まで可能です。 詳細は、本ページを参照ください。(原則、稽古時男女別です) |
||||
| 点前稽古はもちろん、礼儀作法から茶の湯知識、裏方技能、大寄茶会お点前・亭主参加、正式な茶事を亭主・客ともに自然にできる様に目指します。指導者育成や茶の湯探究も実施しています。 (研究会・口伝・特別口伝会・特別研究会 実施) | |||||
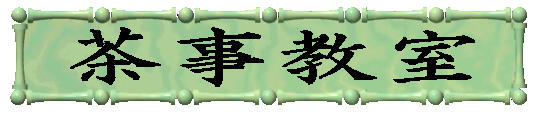 |
表千家は、本来「茶事」を学ぶ流派です。各種茶事を学んでまいります。月1種類2回(初座と後座に分離)、茶懐石は会席料理屋から食材(調理済)、亭主・客を会員交代で実施します。 ※他流派の方も茶事教室に入会可能です。茶事は特に本筋は流派の違いは少ないです。ご自身の点前作法(濃茶、薄茶、炭点前、懐石差異)で、亭主を実行願います(注:指導は、表千家です。) 【月1回 第2木曜日: 原則5時間稽古】 |
||||
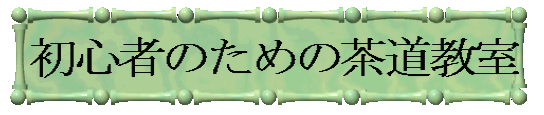 |
初めての方から経験者迄、基礎から茶会での客作法、薄茶点前、濃茶点前を中心に稽古を行います。 大寄茶会参加と正しい所作が自然にできる様、学んでまいります。 | ||||
| 【サバスホール文化教室】 初心者は、各教室共受け付けております。 港南中央教室、上大岡教室、戸塚教室、海老名教室ほか |
|||||
| 【カルチャーセンター・アグリ 上大岡 第1・第3水曜日:午後】 [表千家茶道講座] | |||||
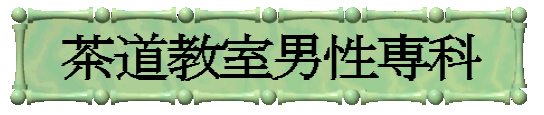 |
男性専科: 創成期は公家・僧侶、武士時代(室町)より江戸時代迄は、武士・商人を中心に伝統を受け継ぎ、多くは男性中心でした。 この区分では、男性のみの教室になります。 |
||||
| 点前・作法は男女に一部異なります。それを除き稽古内容は「本科」と同じ。 ※原則、女性とは時間分離します |
|||||
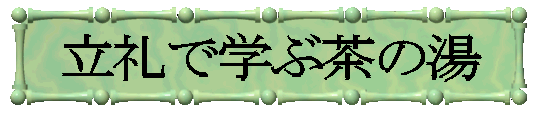 |
立礼で学ぶ茶の湯:
初めての方、正座が苦手な方、お楽に椅子席にて茶の湯の素晴らしさを味わう事ができます。抹茶・お菓子の頂き方、客作法から基礎稽古・御薄・濃茶点前・習事までを実施いたします。 |
||||
| 【有燐堂・戸塚カルチャーセンター 第1・第3木曜日:午後/夜 開講】表千家茶道講座 |
|||||
| 学校茶道部指導 |
ニ校、茶道部指導 (同全校、表千家学校茶道登録校) 高校は、県が所管する神奈川県高等学校文化連盟茶道部会加盟 ※学校茶道教育 横浜市内校 正課・課外・臨時・特別講座など相談に応じます。] |
||||
| 企業茶道部顧問 | 企業茶道部顧問(2社限定):現在F社N工場茶道部顧問 ※茶道部新設に関して相談に応じます | ||||

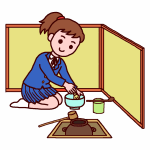








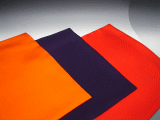


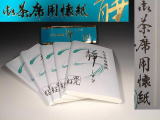













 .
.

